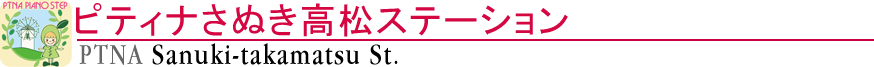2019年4月高松春季ステップレポート
2019年4月20日と21日の二日間、サンポートホール高松4F第一小ホールにて高松春季ステップ(1)(2)を開催いたしました。アドバイザーに添田みつえ先生、ピアノデュオドゥオールの藤井隆史先生、白水芳枝先生をお迎えし、学びに満ちた二日間を各部の様子と継続表彰写真、ご講評、ワンポイントレッスンの順に振り返って参ります。
初日の第1部、第2部は小学校低学年から大人まで幅広い年齢層の方々による、それぞれがピアノとどう向き合っているかが強く伝わってくる演奏でした。コンペを控えた小学生たちは課題曲中心にしたセットリストで、日ごろから真面目に練習している丁寧な演奏。中学生~大人の方は、生活との両立を目指しながらピアノを続けている方が多く、「ピアノが好き!」「こんな風に弾きたい」というこだわりが演奏から伝わってきました。特に、習って5か月目という大人の方が暗譜でチャレンジした中島みゆきの「糸」。とても温かい音色で心のこもった演奏に会場が感動に包まれました。

二日目の1~3部は、幼児~小中学生の多いプログラムで、年齢が進むにつれソロだけでなく連弾やカホン、バイオリン、歌唱など様々なアンサンブルが楽しめるようになり、選曲の幅も広がるなど、可能性を感じる非常に楽しい時間でした。。

小学校低学年の子供たちは、自分のピアノだけでなく他楽器にいかにアンテナを張れるかと挑戦する様子。年齢の高い方のアンサンブルからは、ハーモニーを感じる喜び、アンサンブルの楽しさが伝わる、そんなみずみずしい演奏の数々でした。その継続表彰の様子です。

4~5部はコンペを意識した出場者が多く、各時代らしさの追求、拍やペダリング、指のテクニックの習得など、明確な目標を持った演奏が多く続きました。同じ課題曲でも弾く人によって個性が感じられ、改めて模倣ではなく答えは一つではないこと、何を伝えたいかそれぞれがよく考えて表現することの大切さを目の当たりにしました。その継続表彰の様子です。

6~7部は、さらに上を目指す学習者、音大受験を目指す方、大人になってからも深くピアノを楽しんでおられる方々の味わい深い演奏が続きました。前の部に続き「こうなりたい」と強い意志を持った演奏、その方の人生そのものが年輪のように感じられる、心打つ演奏の数々でしたが、遅い時間ということもあり聴衆が少なく非常にもったいないこと、1人でも多くの方に聴いて頂くための工夫が必要など、今後の課題も残りました。その継続表彰の様子です。

そんな私たちに、アドバイザーの添田みつえ先生、白水芳枝先生、藤井隆史先生は温かく具体的なご講評をくださいました。先生方が共通におっしゃったことが、調性を感じること。特にバスラインや和音など、中~低音部は♯系♭系をはじめ調のカラーを出す役割が大きいこと、それを感じることでより作曲者の思いに近づくことが出来ることをアドバイスくださいました。また、添田先生からはスタッカートやトリルを無理なく美しく響かせるための指のトレーニング方法をご紹介くださいました。
また、白水先生からグランミューズの方について、大人の体の変化と演奏技術の維持という相反する葛藤の中で心打つ演奏は決して技術だけではない、その方の生きていた時間が凝縮されて音で表現されることがどれほど大切か、是非多くの方と共有して頂きたいというメッセージをくださいました。
また、藤井先生と白水先生からはピアノ連弾について踏み込んだアドバイスも多く頂けました。四手をよく聴き音量バランスを考えること、相手を感じること。 そういった情報処理がソロよりはるかに多いという意味で難しく、奥深いこと。 2人で作り上げることによってどんな効果が得られるか、どんな「今日のベスト」を目指すか、その都度二人で目標を設定しながら練習するとよいことをアドバイス下さり、「ソロも連弾も、どんな練習も本番も全ての音楽を感じる時間は繋がっており、弾けた先にある喜びを感じてくださいね」とメッセージをくださいました。

添田みつえ先生、白水芳枝先生、藤井隆史先生、ありがとうございました。
藤井隆史先生と白水芳枝先生によるワンポイントレッスンは、ご講評頂いたことを実際にステージで実践される様子を会場の皆さんで見て学ぶ貴重な時間でした。

連弾ではセコンド、バスラインが推進力になり、内声はバスの中に完全に入る音量にする。年齢差も含めた音量バランスのコントロールにも気を配ることで、より一体感ある演奏に変わりました。

ピアノソロでも、各声部の役割を整理し音量バランスに気を配ること。長いフレーズの途中で息切れしないよう、計画性方向性、目的地を常に意識することで、より色鮮やかな演奏に変化しました。
トークコンサートでは、ピアノデュオ ドゥオールの藤井隆史先生、白水芳枝先生による「春が来た!」と題して、ブラームス「ワルツ」、ヨハンシュトラウス2世「美しき青きドナウ」、ラヴェル マ・メール・ロワより「妖精の園」、ブラームス「ハンガリー舞曲5番」が演奏されました。

ピアノから、ティンパニのような低音、木管楽器の柔らかい音色、波のような弦楽器の音が次々にあふれ出し、会場中が魅了されました。演奏だけでなく、舞曲と音楽の関係のお話や演奏準備中のちょっとしたコツなど、ここでも1秒を惜しんで多くのアドバイスをくださいました。藤井隆史先生、白水芳枝先生、ありがとうございました!

最後になりましたが、毎回高松のステップに出演させて頂いている高松バスティン研究会鍵盤ハーモニカ部コンセールオリヴィエの集合写真をご覧いただいて、レポートを締めくくらせて頂きます。

今回はお誕生日を迎えられたばかりの白水先生に、トークコンサート後に客席からコンセールオリヴィエによる「ハッピーバースディ」のサプライズ演奏がありました。そんな楽しいひと時を含め、熱い二日間を多くの方と共有でき、ステーションスタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございました。
さぬき高松ステーション
2019年4月20日と21日の二日間、サンポートホール高松4F第一小ホールにて高松春季ステップ(1)(2)を開催いたしました。アドバイザーに添田みつえ先生、ピアノデュオドゥオールの藤井隆史先生、白水芳枝先生をお迎えし、学びに満ちた二日間を各部の様子と継続表彰写真、ご講評、ワンポイントレッスンの順に振り返って参ります。
初日の第1部、第2部は小学校低学年から大人まで幅広い年齢層の方々による、それぞれがピアノとどう向き合っているかが強く伝わってくる演奏でした。コンペを控えた小学生たちは課題曲中心にしたセットリストで、日ごろから真面目に練習している丁寧な演奏。中学生~大人の方は、生活との両立を目指しながらピアノを続けている方が多く、「ピアノが好き!」「こんな風に弾きたい」というこだわりが演奏から伝わってきました。特に、習って5か月目という大人の方が暗譜でチャレンジした中島みゆきの「糸」。とても温かい音色で心のこもった演奏に会場が感動に包まれました。

二日目の1~3部は、幼児~小中学生の多いプログラムで、年齢が進むにつれソロだけでなく連弾やカホン、バイオリン、歌唱など様々なアンサンブルが楽しめるようになり、選曲の幅も広がるなど、可能性を感じる非常に楽しい時間でした。。

小学校低学年の子供たちは、自分のピアノだけでなく他楽器にいかにアンテナを張れるかと挑戦する様子。年齢の高い方のアンサンブルからは、ハーモニーを感じる喜び、アンサンブルの楽しさが伝わる、そんなみずみずしい演奏の数々でした。その継続表彰の様子です。

4~5部はコンペを意識した出場者が多く、各時代らしさの追求、拍やペダリング、指のテクニックの習得など、明確な目標を持った演奏が多く続きました。同じ課題曲でも弾く人によって個性が感じられ、改めて模倣ではなく答えは一つではないこと、何を伝えたいかそれぞれがよく考えて表現することの大切さを目の当たりにしました。その継続表彰の様子です。

6~7部は、さらに上を目指す学習者、音大受験を目指す方、大人になってからも深くピアノを楽しんでおられる方々の味わい深い演奏が続きました。前の部に続き「こうなりたい」と強い意志を持った演奏、その方の人生そのものが年輪のように感じられる、心打つ演奏の数々でしたが、遅い時間ということもあり聴衆が少なく非常にもったいないこと、1人でも多くの方に聴いて頂くための工夫が必要など、今後の課題も残りました。その継続表彰の様子です。

そんな私たちに、アドバイザーの添田みつえ先生、白水芳枝先生、藤井隆史先生は温かく具体的なご講評をくださいました。先生方が共通におっしゃったことが、調性を感じること。特にバスラインや和音など、中~低音部は♯系♭系をはじめ調のカラーを出す役割が大きいこと、それを感じることでより作曲者の思いに近づくことが出来ることをアドバイスくださいました。また、添田先生からはスタッカートやトリルを無理なく美しく響かせるための指のトレーニング方法をご紹介くださいました。
また、白水先生からグランミューズの方について、大人の体の変化と演奏技術の維持という相反する葛藤の中で心打つ演奏は決して技術だけではない、その方の生きていた時間が凝縮されて音で表現されることがどれほど大切か、是非多くの方と共有して頂きたいというメッセージをくださいました。
また、藤井先生と白水先生からはピアノ連弾について踏み込んだアドバイスも多く頂けました。四手をよく聴き音量バランスを考えること、相手を感じること。 そういった情報処理がソロよりはるかに多いという意味で難しく、奥深いこと。 2人で作り上げることによってどんな効果が得られるか、どんな「今日のベスト」を目指すか、その都度二人で目標を設定しながら練習するとよいことをアドバイス下さり、「ソロも連弾も、どんな練習も本番も全ての音楽を感じる時間は繋がっており、弾けた先にある喜びを感じてくださいね」とメッセージをくださいました。

添田みつえ先生、白水芳枝先生、藤井隆史先生、ありがとうございました。
藤井隆史先生と白水芳枝先生によるワンポイントレッスンは、ご講評頂いたことを実際にステージで実践される様子を会場の皆さんで見て学ぶ貴重な時間でした。

連弾ではセコンド、バスラインが推進力になり、内声はバスの中に完全に入る音量にする。年齢差も含めた音量バランスのコントロールにも気を配ることで、より一体感ある演奏に変わりました。

ピアノソロでも、各声部の役割を整理し音量バランスに気を配ること。長いフレーズの途中で息切れしないよう、計画性方向性、目的地を常に意識することで、より色鮮やかな演奏に変化しました。
トークコンサートでは、ピアノデュオ ドゥオールの藤井隆史先生、白水芳枝先生による「春が来た!」と題して、ブラームス「ワルツ」、ヨハンシュトラウス2世「美しき青きドナウ」、ラヴェル マ・メール・ロワより「妖精の園」、ブラームス「ハンガリー舞曲5番」が演奏されました。

ピアノから、ティンパニのような低音、木管楽器の柔らかい音色、波のような弦楽器の音が次々にあふれ出し、会場中が魅了されました。演奏だけでなく、舞曲と音楽の関係のお話や演奏準備中のちょっとしたコツなど、ここでも1秒を惜しんで多くのアドバイスをくださいました。藤井隆史先生、白水芳枝先生、ありがとうございました!

最後になりましたが、毎回高松のステップに出演させて頂いている高松バスティン研究会鍵盤ハーモニカ部コンセールオリヴィエの集合写真をご覧いただいて、レポートを締めくくらせて頂きます。

今回はお誕生日を迎えられたばかりの白水先生に、トークコンサート後に客席からコンセールオリヴィエによる「ハッピーバースディ」のサプライズ演奏がありました。そんな楽しいひと時を含め、熱い二日間を多くの方と共有でき、ステーションスタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございました。
さぬき高松ステーション