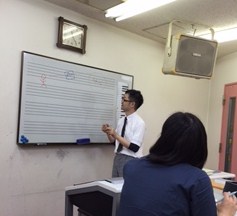第28・29回アナリーゼ講座
◆2015年7月16日(木) 10:15~
9月17日(木) 10:15~
◆場所 和幸楽器大宮店
◆講師 西尾洋先生
◆内容:
メンデルスゾーン「無言歌集」より
・瞑想
・ベニスのゴンドラの歌Op.30-6
・過ぎ去った幸福
・二重唱
・浮き雲
・プレストアジタート
夏休みを挟みましたが、7月と9月の2回に分けてメンデルスゾーンの無言歌集から数曲の
アナリーゼをしました。(5月にも第1曲目の"甘い思い出"を勉強しています。)
どの曲についても、西尾先生独特の素敵な表現による解説があり印象的でしたので少しずつ記録させて頂きます。
「瞑想」
ショパンは右でメロディ、左で伴奏(アルペジオ)というスタイルを取ることが多かったが、
メンデルスゾーンは右と左でアルペジオを取りながらその音域の中で表現をし、味わいを出
している。
同じ楽譜の「模様」が2回続いた時に表現を変えることで、人の心に伝わる。
「ベニスのゴンドラの歌」
いつもバスに響きを合わせる、バスを聴く。
中間部からそのバスが動き始める。
フォルティッシモの所では、左が曲を引っ張る。
「過ぎ去った幸福」
弦のボーイングが意識されたスラーが書かれている。
左の伴奏形ノリズムは、心のやり切れなさ、葛藤を表している。
「二重唱」
ヴァイオリンとチェロをイメージして、2つのパートの受け渡しを考えて演奏する。
不協和音のぶつかりは美しく。不協和音にこそ表情がある。
32小節目で2つの楽器はユニゾンになる。特別感動的な場面。
「浮き雲」
1拍目は必ずそろえる。
右に左を合わせる。アウフタクトで惑わされないで。
「プレストアジタート」
1小節ひとつのハーモニーで始まる。
各小節の右の最後にあるスタッカート記号の弾き方は?
そして、全曲を通して非常に心に残ったことは、テンポも表現方法の一つである、特にロマン派に
おいては大切なことである、という部分でした。
espressivoやdolce、クレッシェンドやdim.をテンポと関連させてみるということを解説の随所にお話され、早速実践したいと思うことが出来ました。
「楽譜は未完成な設計図」であり、作曲家の思いは楽譜に全て書かれている訳ではないというお言葉も、なるほどその通りですね。
毎回作曲家の視点から楽譜の読み方のヒントを与えて下さる西尾先生、本当にありがとうございます!
連続して続いたメンデルスゾーンは一度終了し、次回からは別の作曲家(秋にふさわしい方・・・)が登場することになりました。
こちらもまたとても楽しみです。
< 文責:大原由紀 >