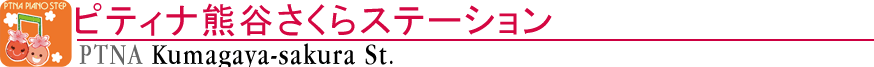5月22日に開催された熊谷春季地区ステップ会場で、
5月22日に開催された熊谷春季地区ステップ会場で、
アドバイザーの小倉郁子先生による親学レクチャーが行われました。
ステップで小倉先生が『親学レクチャー』をなさるのは、初めてということでした。
第1回、第2回ともに、15分ずつという短時間での講義でしたが、
多くの保護者の方やピアノ講師の皆様にお集まりいただき、
当レクチャーへの関心の高さを感じました。
小倉先生は、双子の息子様の子育てをされたお母様としての視点から
ピアノを核とした教育論をお持ちの先生です。
お子様を授かられる前から、ピアノの先生として多くの子供さんを指導されていたので、
一般的な『お母さん』よりも、ご自身のお子様方を客観的に見ることが出来たかもしれないとおっしゃっていました。
以下は小倉先生のお話を、文章にさせて頂きます。
言い回し方や、文脈が先生の言葉と異なる箇所があります。
ご了承ください。
レクチャー1 ~成功へのサイクルとは~
◎わが子の子育てから生きたサイクルを見つけました。体験談をお話しします。
ピアノという習い事は、『家庭学習』です。
家族がつぶさに見ている環境で練習を重ねていくものです。
小学校低~中学年までは、是非『親子で』取り組んで頂きたいと思います。
全てに通じる基礎力をつける時期に、それはとても重要です。
先生にお任せには、しないで頂きたいです。
なぜなら......
ご自分のお子さんが
今、「何に悩んでいるのか」「何に困っているのか」がわからなくなってしまうのです。
『親子で真剣に取り組む』とは具体的にどのようなことでしょう?
いつも何時間もくっついて...ではなくて良いのです。
親御さんにはレッスンを見学して頂きます。
先生のレッスンで習ってきた練習の仕方があるとしましょう。
親の方が理解力を持っているのですから、どういうふうに...、というやり方をお家で再確認し、
教えてあげて下さい。そして、『家庭学習』として身につけて行きましょう。
また、先生はレッスン中によく比喩や、抽象的な表現を用いますが、お子様によっては
その表現よりわかりやすい生活体験や言葉掛けがあると思います。子供さんに合う噛み砕いた言葉での説明は、
その親しかできない役目だと思います。親子だから伝わることがあるのです。
子供の性格(まったく考えようとしない。すぐメソメソ泣いてしまう等...)は何故そうなのだろう?と
日々の生活を観察しながら、親御さんにも学んで頂きたいと思います。
日々の生活を観察することは、その子供へ反抗期や受験期にどんな言葉掛けをするのが良いか、
知っていくことに繋がる大切な事と考えています。
また、『親子で真剣に取り組む』ことは、親子の絆に繋がります。
厳しい半面、愛情たっぷりに、やるならとことん本気で!
時には子供を崖っぷちに立たせてみることも必要です。例えばPTNAのステップやコンペを利用して、
厳しい岐路に立った時に、最後は自分の力で解決できる『強い精神力』をつけるための経験を
させてあげてください。
その経験をさせた後、出来具合によって、がっかりしてしまう親御さんがいらっしゃるかもしれません。
そんなとき、絶対にしてはいけない言葉掛けがあります。
『やめちゃいなさい』です。この言葉を発してしまった時、親御さんはその子供の教育に負けてしまっています。
さて、目標に向かってとことんやり抜くということは、小学高学年まで意識して取り組むことが大切です。
サイクルを何度も何度も積み重ねて経験させることで、サイクルが身に付きます。
そのサイクルは
目標→継続→努力→達成感(喜び、自信)→新たな目標→継続にもどる...
というものです。
ただし、タイムリミットがあります。
子供の反抗期の前までに親子の絆づくりをしてください。
レクチャー2 ~ピアノ学習から何を学ぶべきか~
◎ピアノ学習者を核にして考える子育て法を伝授します。
ピアノ学習とは、楽譜があって読譜をし、イメージを膨らませ、それを音にするためのテクニックをマスターする『表現訓練』と言えると思います。
『読譜』とは、左右、両手がすらすら弾けるようになったら終わりではなく、音楽理論を手掛かりに曲を分析することと、作曲家の時代背景などを合わせて読み取る『知的アプローチ』も含めて考えなくてはなりません。
その中には学ぶものが多く、人として成長するのに必要なことが沢山詰まっています。
目標に向かって時間や労力をかけて、立ち向かっていけるように
『集中して取り組める環境』を提供してあげてください。
子供がくじけた瞬間に指導者はどう支えればいいでしょう?
努力を認めてあげつつ、今乗り越えようとしているハードルを、出来るだけ小さなハードルに出来るよう工夫しましょう。
また、何度も時間をかけていると、何を目的にしているのか忘れがちになります。
いつも目的意識を忘れずに持って取り組めば、練習は捗ると思います。
保護者と指導者は、ピアノ学習の過程を、常に『情操教育』であると認識していなければなりません。
ピアノを通じて『人づくり』をしているのです。
レクチャー1でもお話ししたように、ステップやコンペに挑戦し、やるならばとことん取り組み、
自分を苦しいところに敢えて追いやることで、人間形成に役立ちます。
豊かな心を育て、自己を戒め、限界まで頑張るということはもちろん、
限られた時間の中で練習することで、時間配分や自己管理が出来るようになります。
また、どう練習すれば効率よくこなせるか?どう表現しようか?など、
創意工夫ができるようになっていくと思います。
忙しくなる中高生に成長したとき、自分で優先順位を考える力や自己コントロール、目標に向かってやり抜くことを自然に身につけていけると考えています。
その様に成長できるよう、親は子供の年代が小さいうちから言葉掛け、アドバイスをしてください。
とことん取り組み、ステップやコンペで演奏することで得られるものは、なんでしょう?
仕上げた曲を人の前で演奏する時、その本人は「期待」「不安」「緊張」と闘いながら、奮闘しています。
このステージ経験は、本番でしか出来ないのです。ここ一番という時に自己管理をし、実力発揮する訓練が出来ると思います。
この経験は人生のなかで様々な機会に、きっと役立つことと思います。
以上が親学レクチャーでのお話でした。
保護者、指導者にとって、大変興味深いお話でした。
もっとお話を聞いてみたい!と多くの皆様が感じられたのではないでしょうか?
今回のお話をお役立て頂き、是非ピアノを『人生の友』として頂けたら幸いです。
報告者 古川 貴子