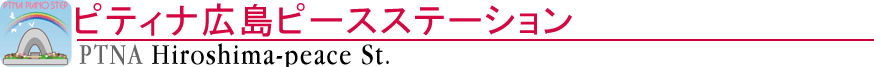7月23日広島中地区広島ピースステーションではこの度初の試みとなる調律師による『ピアノぷち構造学~のぞいてみようペダルのしくみ~』を開催いたしました。
講師はステップの会場 広島市南区民文化センターホールピアノ専任調律師でヤマハミュージックリテイリング広島店嘱託、ピティナ調律会員の宮尾正樹さんです。
♪ 早速ピアノの中をのぞいてみましょう!
ペダルをふんだ時、はなした時、ピアノの中ではどんなことが起きているのかな?
ステージのピアノのまわりに約40名の子供たち、保護者の方、ピアノの指導者のみなさんが集まりました。鍵盤のふた、そしてネジを外してピアノの鍵盤アクションを取り出すと精巧なメカニックが現れ「わぁ~」と歓声が...

♪ ペダルのひみつ
「3本のペダルそれぞれの名前と役割(効果)について知ってるかな?」
「ダンパーってどの部分か指さしてみて?」
クイズも交えながら調律師さんの解説がすすみます。
ハンマーで弦を叩く役目のお子さん、鍵盤側からペダルを踏んでダンパーを操作するお子さんと分担して、ペダルをゆっくり上げた時とパッと上げた時と実験を繰り返しながら残響の違い、音の切れ方(消え方)の違いをみんなで体験しました。
 ハンマーもダンパーも羊の毛で作られたフェルトで出来ていますが、硬さが全然ちがいます。硬く圧縮されたハンマーのフェルト、柔らかく弾力のあるダンパーのフェルトも実際に触り比べ、それぞれが果たすピアノのパーツとしての役割についても解説して頂きました。またペダルには踏み始めてペダルの効果が表れるまでのあそびの部分が設けられていること、ハーフペダルについてもみんなで目視確認をしました。
ハンマーもダンパーも羊の毛で作られたフェルトで出来ていますが、硬さが全然ちがいます。硬く圧縮されたハンマーのフェルト、柔らかく弾力のあるダンパーのフェルトも実際に触り比べ、それぞれが果たすピアノのパーツとしての役割についても解説して頂きました。またペダルには踏み始めてペダルの効果が表れるまでのあそびの部分が設けられていること、ハーフペダルについてもみんなで目視確認をしました。
実際に目で見て、触れてみることでペダルは単純にオンとオフではないこと、踏み方によって響きやフレーズの閉じ方が変わってくることを実体験として学ぶことができました。ピアノの弦を打つ本物のハンマーのお土産もみんな1本ずついただきました。

♪ 調律は大切!
講座のしめくくりにステーション代表の沖根典子先生が調律師の仕事は音律を整えるだけでなく、鍵盤の動き、ペダルの動きが円滑であるよう調整するのも仕事で、調律師がいないとせっかく練習してもいいパフォーマンスが発揮できない...と調律の大切さについても言及して下さいました。会場からは講師役を務めて下さった調律師の宮尾さんに大きな拍手がおくられ、ピアノへの興味・理解が深まる機会になったと思います。
これからもみんなで一緒に楽しく学んでいきましょう!
(ピティナ広島中央支部事務局:中津美和)